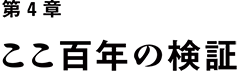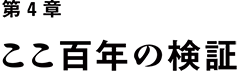
- 山口
- 今、愛知万博(※取材時は2005年6月)が開かれていますが、ちょうど100年前にパリ万博が開かれた。そうしたここ100年の動きというのは、実はものすごく大きいのではないかと思うのですがいかがでしょう。
- 伊東
- そもそも「日本画」というのも、明治時代に西洋から開国するよう迫られたときに作った概念で、たかだか100年くらいのものなんですよね。明治期に入るまで「日本画」という言葉も「芸術」という言葉もなかったわけで、西洋の「アート」に対するものを「芸術」として、この「国」の独自な「アート」として「日本画」というものを作った。で、今の自分は「日本画」もへったくれもなく「現代美術」としてやればいいんだよ、という開き直りがあってやってきたんですが、その「現代美術」というものが、当たり前ですけど西洋のコンテンポラリーアートをベースにしている。ヨーロッパ型のコンテンポラリーアートを日本は導入、というか平行輸入して「文物化」して、いわば向こう側の流儀をこちら側の解釈で読み解き、それをぼくらは「日本の現代美術」として理解したり作ったりしている、という認識と暗黙の了解事項があると思う。でも、それってかなり無理なーー全面否定はしませんけどーー、不自然なことをやってるような気がします。日本に今のような形で「現代美術」は本当に必要なのか? それを「芸術」と呼ぶ必要があるのか? という根本的な問いがずっとあります。僕個人はある時期からなぜヨーロッパ、またはアメリカ型のアートの概念に則した流儀で作品を考えたり、作ったり、観たりしているのかがよく解らなくなってきて、そういった意味での「現代美術」に意味を見い出せなくなったんですよ。と同時に逆に自分を解放できた。かなり縛られていたんだと思うけど、もういいじゃん、って。そんな流儀にあわせる必要ないじゃん、と思って。で、好きなことをやり出したんです。それが「芸術」でも「美術」でも「音楽」でも、なんでもいいし、観る人に何と思われてもいいやって。
- 山口
- それがオプトロンをやり始めた頃ですね。
- 伊東
- 「聴覚表現」と「視覚表現」の垣根は、何しろパンク、ニューウェーヴ世代なんでサッさとスッ飛ばして(笑)。恥知らずというか、無頓着というか、故に救われているとも思うんですけど。そんな感じでオプトロンをやり始めた。だから「現代美術」にはさほど恩義は感じてないんですよ。どっちかというとずっと聴いてきた音楽のほうによっぽど恩義を感じます。もらったものは明らかにそっちの方が大きかった(笑)。
- 山口
- 伊東さんにとって日本人である、ということの意味は?
- 伊東
- この国に「現代美術」という枠組みは必要なのか云々、と言いましたが、それを考えてゆく上でも、もっと自分の身の回りのことを考えるにしても、自分が今いる『ここ』の地域性というのはどうしても無視はできないですね。作り手側の意識としては、地域性や歴史というものを感じないわけにはいかないし、それを意識するのか、しないのかも含めて、ここでの生活者としての側面があるわけですし。そうするとヨーロッパともアメリカとも明らかに違った地域性がある。「古来」や「伝統」といってもいつから「古来」なのか知らないし、僕にとっては還れる「古来」は今更ないんじゃないかとすら思いますし。ただ「偶然この地域でこの時間に生まれ育った」ということが、唯一還れる場所なんじゃないでしょうか。この「日本」と呼ばれる地域の、白黒テレビがカラーテレビになり、どこでもスイッチをいれたら蛍光灯がつくようになった時期に、何不自由なく育ってきた体験がベースにあり、それ以上のものがあるわけでもない。1965年生まれの僕にとってすごく解りやすく西洋と対比できる東洋としての「日本」を感じてきたわけではないし、アメリカナイズという言葉に象徴されるような解りやすいアメリカというものも肌身に感じたわけでもない。「かつて在った日本らしさ」と言われるものに触れたときのほうが違和感を覚えることが多かったし、かといって「多国籍」な環境が身近にあったわけでもない。日本が、東京が、ただ、そういう「在り方」の地域だっただけで。全部入り交じった状態、それが僕のニュートラルな状態だと思うし、それが僕が感じる「日本」だし、そう思える僕は「日本人」なんだろうと思います。ことさらそのことを意識するわけではないですけど。
- 山口
- 今、見直しのときということでしょうか。
- 伊東
- 結局、西洋の枠組みを導入したのはいいけど、その時に何をすっ飛ばしたのか、何をどう合理化したのか、そのあたりの整理がずっとつかないまま今まで来ているような気がします。故にそれらのことは、僕らにほとんど知らされてないんじゃないかな。そもそも日本にヨーロッパのような「モダン」ってあったんだろうか? そういった検証を行きつ戻りつ考える必要はあるだろうし、それは誰かによって少しでも検証されていると思いたいです。でも言ってしまえば、それも僕個人の課題でいいんですけどね。社会的な大義名分は必要ないですし、いまさら。国に期待してもしょうがないし。僕にとって観たいこと、知りたいことの1つなんです。なぜこういうことになっているのか?ということは。多分、いわゆる「芸術」の分野だけの話ではないと思いますが、この100年の良くも悪くもどこか「奇形化」した日本の生んだズレがこうなってると感じるし、もはやそのズレそのものがこの国の「文化」だとも思えますけどね。
- 山口
- ズレといえば平安時代の昔から、外から取り入れて変なものを生むのが日本ですよね。
- 伊東
- 例えばここ15年くらいの日本のアヴァンギャルドな音楽とかがわかりやすいと思うんですけど、西洋の音楽史観で読み解こうとすると、ある種の奇形というか、理解不能なものが日本のそれらには在ると思うんですよ。それはこの地域が生んだ強さでもあると思うんです。だってあちらから見たら「無根拠」だと思うもん(笑)、日本の音楽は。ただ、それがどこから来てどこへ行くのかは、僕はもう少しだけ意識的に考えたい。でもそれはアカデミズムではなく、あくまで個人の興味と探究であって、個人でやればいいことだと思います。