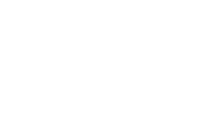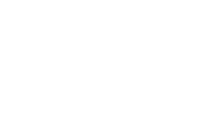
- 高木
- この2年間、ほんとうにいろんな方に出ていただいたけれど、毎回、毎回面白かったですね。無名な人も有名な人も、老いも若きもいろんな方がいましたが、何かを求めている人は「強い」と感じました。
- 山口
- それは私も感じました。様々な形ではあれ、中に「強さ」を秘めている。だからこそ何かを創造したり表現することができているんでしょう。
- 高木
- みんなとても濃密な世界を持つ人たちで。いつの間にか彼らの濃さに慣れてしまい一歩外に出ると世の中の薄さが際立ってしまう。ああした濃い世界を持つ人たちって、結局、マイノリティなんだと感じるんです。彼らはこの資本主義の世の中で、中心ではないエッジにいる人たちなんですよ。
- 山口
- それは確かにそうですね。この資本主義社会で、どうやって生きているんだろう、という人も多かった。
- 高木
- そういう意味でジレンマも抱えているはずなんです。大勢に流されるほうが楽なわけだから、流されないように立ち続けることは、ある意味、苦しいことであると思う。
- 山口
- だからこその強さだと思う。この資本主義の世の中で、そうじゃない形で一生懸命生きているから、だからみんな強いんですよ。
- 高木
- 小夜子さんが面白いな、と思うのは……もともと世界のトップ・モデルの走りで、ファッションのコアな世界にいたでしょう。それはある意味、資本主義社会の中心にいたということでもあって、そこにいた人が今、社会のエッジにいる人と資本主義社会の中心にいる人とのメッセンジャーになっているのが面白いと思う。独自の世界を持ちエッジに立つ人が社会にこうして波紋を投げかけているよ、とみんなに知らせるメッセンジャーに。いつからそういう立場になったんだろう、というのが不思議で。
- 山口
- それは最初からなんです。もともと私はどちらかというとエッジの側にいて、ある瞬間、資本主義社会の中心にいる人々から興味を持たれて、接点が生まれただけなの。私自身、そのときはジレンマも感じていたと思います。
- 高木
- それはたとえば化粧品会社の仕事をしていたときも?
- 山口
- 広告のお仕事そのものは興味深いものでした。髪型やアイラインの入れ方、まつげの上げ方、唇の色や形、肌の質感も含めて、独自のイメージを写真家やメイクの方達と共にクリエイションするのは楽しい作業でした。それはこの蒙古班革命の始まりでもあったとも思います。ただ、ブームに関しては、私の中でちょっと待って、もっと見つめるべきことは他にあるんじゃないか、とずっと思っていて。
- 山口
- モデルとしては変な人と思われていたかも知れないけれど(笑)。与えられたものをそのままではなく、それをさらに逆転して考え、壊して組み替えて返す、ということはしていました。その部分を喜ばれたんだと思う。だからむしろ作る側の人たちとの交流が多くて、アトリエの人たちと何かを創造する瞬間が楽しかった。以前は、あるものの中に自分が入って、ほんのちょっと1mm、2mmを変えていくことしかできないという葛藤もあったけれど、今ではこちら側に人が 来てくれることが増えたので。一緒に一から創ることができるので、今、とても楽しいんです。やはりクリエイションの現場が楽しいですね。
- 高木
- 根っからのクリエイターなのね。何かを創ること……私はプロジェクトと呼んでいるんだけれど。人生=プロジェクトだと思っているんです。小さくてもいい。3つでも4つでもプロジェクトを抱えていて、これはやってみよう、これは今はしまっておこう、と少しずつ小出しにして。漠然と生きていると、仕事をこなすだけで日々が過ぎていってしまうでしょう。でも何かを産み出す、何かを創り出すというプロジェクトを抱えていると、急に人生が楽しくなるの。